
K-1“生みの親”石井館長が明かすヘビー級から始めたワケ「デカいヤツがバチバチ殴り合えば…」
2023年は、1993年にK-1が誕生してから丸30年に当たる。そこで“生みの親”である石井和義館長(正道会館宗師)を直撃。REBIRTH(再生)を掲げたK-1における方向性や、さらにはK-1の母体だった正道空手による「KARATE GRAND PRIX」についても話を聞いた。
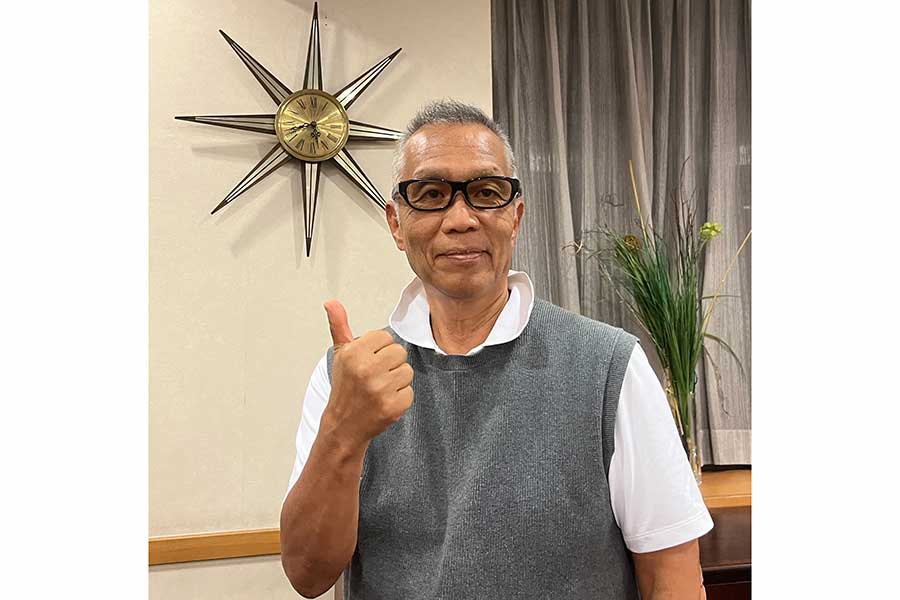
30年前と真逆の戦略
2023年は、1993年にK-1が誕生してから丸30年に当たる。そこで“生みの親”である石井和義館長(正道会館宗師)を直撃。REBIRTH(再生)を掲げたK-1における方向性や、さらにはK-1の母体だった正道空手による「KARATE GRAND PRIX」についても話を聞いた。(取材・文=“Show”大谷泰顕)
去る12月9日、エディオンアリーナ大阪で開催されたK-1に、生みの親である石井和義館長の姿があった。
「新生K-1になってから初めて見たんですよ。招待していただいたので。K-1を見るのは10年ぶりかな」
大会終了後、石井館長は自身のXに以下の投稿をポストした。
「2024年3月20日にK-1MAXがK-1誕生の地である、代々木第一体育館でスタートする。K-1ブランドを世界に再構築するのは中量級でインパクトを与えて、ヘビー級で世界を揺るがし、軽量級の”人類最速スピード”で日本選手の強さを知らしめること。だからMAXからなんだ。順番とても大切だよ」
実はこの「順番」という言葉に引っかかりを感じた。というのは30年前の1993年、最初にK-1を立ち上げた際は、8人のヘビー級ファイターによるワンデートーナメントだった。そこから9年後の2002年に初めて、魔裟斗を主軸にした中軽量級のMAXが誕生。いわば30年後の今、K-1は30年前と真逆の戦略を取ろうとしている。
石井館長が答える。
「今から30年前の1993年はプロレス全盛時代だったのよ。今は信じられないかもしれないけど、プロレス団体が20団体くらいあって、GWだと福岡ドームでは新日本、川崎球場では大仁田厚対ミスター・ポーゴ(FMW)、日本武道館では全日本プロレスがやっていて、日本にあるデカい会場では全部プロレスをやっていた。しかもどこも満員だよ」
当時をそう振り返った石井館長は「なおかつターザン山本編集長がやっていた『週刊プロレス』なんて発行部数が公称30万部あった。『週刊文春』も『週刊ポスト』も真っ青になるくらい売れていて、それが駅のキオスクに出ていてね」とプロレスの持つメディアの特異性を注視していた。
「そんな時代にキックだK-1だってやって、60キロ台の子が試合をしたって、2メートル近くあって100キロ以上あるプロレスラーと比べられたら、強さって感じられるわけがない」
王・長島の横に“キックの鬼”
もちろん日本人だと当時から50キロ台、60キロ台の選手が強いことも分かっていた。
「分かっていたけど、そこから初めても勝負にならないわけよ。僕らのライバルは新日本であり、もっと言えばその頃に始まったJリーグであり野球だったりしなきゃいけないでしょ。だからプロレスラーよりもデカいヤツ同士がバチバチになって殴り合わなければね。それでヘビー級から入ったわけよ。その当時はヘビー級から入るしかなかった。それしか選択肢がなかったの」
当時、日本人のヘビー級選手の主力は佐竹雅昭しかいなかった。
「その後、武蔵や他の選手も出てきてたし、大道塾の長田賢一選手にも出てきてほしかったけど、難しくてね。佐竹をエースにして、角田信朗がいて、それでも日本人が足りないからってことでアンディ・フグやサム・グレコのような極真から来た選手を日本側に入れて対立構造をつくって行った」
石井館長がヘビー級から入ることを決めた、ひとつのエピソードがある。
「印象的だったのは、いつだったか王・長島の横に“キックの鬼”の沢村忠さん(※真空飛びヒザ蹴りで一世を風靡)がいたことがあった。あるいは大鵬、力道山とかね。当時の注目されたスポーツ選手なんだろうな。そしたらやっぱり沢村さんは小さかったんですよ。ライト級だったからね。沢村さんは本当に強い人だったけど、そしたら他の人のほうが強そうに見えた」
巨人・大鵬・玉子焼きの時代、やはりカラダの大きさは重要だったが、いつの世もその感覚は大きく変わることはない。
「でも、ピーター・アーツ、アーネスト・ホースト、ジェロム・レ・バンナ……っていうヘビー級の選手を揃えたら、みんなデカいからね。プロレスラーのほうが小さかったよ。その選手たちがバッチバッチに殴り合うんだから、絶対にこっちに注目が集まるよね。だからヘビー級でスタートしたけど、しばらくして(2002年)から軽いクラスに移行した。なかには185センチくらいの身長の高い選手もいたから、中量級・ミドル級のクラスに移行して、ようやく軽いクラスに順番に持って行こうとしたんだよ。その戦略は悪くなかったと思うよ」
17日開幕の「KARATE GRAND PRIX 2023」
30年前にK-1が誕生した当時、日本人選手の主力だった佐竹や角田、武蔵らは、石井館長が創設した正道会館に所属していたが、17日にはエディオンアリーナ大阪において、正道空手によるオープントーナメント「KARATE GRAND PRIX 2023」と題した、全日本選手権大会が開催される。
ざっくりと分けると、空手には「寸止め」と呼ばれる、直接相手に当てない伝統派スタイル(五輪競技)と、極真空手に象徴とされる、フルコンタクト空手がある。ただ、フルコンタクトといっても、とくに少年がやるとなった場合、安全面を考慮して、顔面だけは叩き合わない、いわゆる顔面ナシの競技体系が取られてきた。
「たしかにルールとしてはそうなんだけど、元々、極真をつくられた大山倍達総裁。僕らは大山総裁が大山館長と呼ばれていた頃に、極真の“ケンカ十段”と呼ばれた芦原英幸先生の芦原道場にいたんだけど、芦原先生から聞いている話では、元々、極真は顔面アリだったと。だから僕らもそういう組手をやっていた。先輩はパー、つまり掌底で叩いて、僕らはグーで先輩にかかっていった。それが極真をつくられた大山館長の教えだと聞いていたから」
しかもグローブを着けるわけでもなく、素手でそれを行なっていたというから驚きだ。
「だから組手では『軽く叩けよ』と言っていたんだけど、元々、大山館長は、顔面アリの大会をやりたかったわけ。だけど顔面を素手で叩き合うと危険だから、顔面アリを想定しながら、大会は顔面ナシで実施した。ただ、練習中は常に顔面アリという心構えでいなくちゃいけない。だってケンカの時に、顔は攻めないでくれ、なんてありえない。顔を叩く、目を突く、頭突きをする、なんて当たり前なんだから。もちろん顔面ナシという、試合のためのルールが発展して今に至るんだけど、フルコンに関しては、僕はそこを懸念してますね」
では、実際の正道空手はどうなのか。
「正道空手は顔面アリを基本とした稽古体系をとっているし、正道空手を習得すれば、キック、ムエタイ、総合にもつながる技術が得られるし、護身術にもなる。もちろん子どもは顔面ナシで叩くけど、大人になったら素手で叩くことも取り入れる。だから今はライトコンタクトをやって、慣れてきたら本格的に叩き合う、『フルコン+(プラス)』という形でやっているんだけど、お互いに最大公約数のルールで闘える方法を取ってますね」
とはいえ、石井館長としては「フルコン+」の普及には、多少は時間がかかると考えているようだ。
「思ったより(大会に参加選手が)出てこないんだよねえ……。やっぱり普段フルコンをやっている人たちは、顔を叩くのは嫌みたい。だけど徐々に広がってきているから、これはゆっくりとやればいいかなあ……という大会を17日のエディオンアリーナ大阪からスタートさせます」
ちなみに「KARATE GRAND PRIX 2023」は入場無料。
「是非、見に来てください」と石井館長はニコリとしながら呼びかけた。K-1が誕生して30年、石井館長は今なお血気盛んに、新しい挑戦をし続けている。
 あなたの“気になる”を教えてください
あなたの“気になる”を教えてください
