
人狼系ゲームのアニメ化はなぜ成功したのか? 『グノーシア』に感じた“見せ方”の工夫
TVアニメ『グノーシア』が各所で大きな話題を呼んでいる。近年、原作がある作品のアニメ化となると、原作ファンからの厳しい目が向けられることも少なくない。しかし本作に対しては、原作ファンも初見の視聴者も高く評価する声がSNSで目立っている。
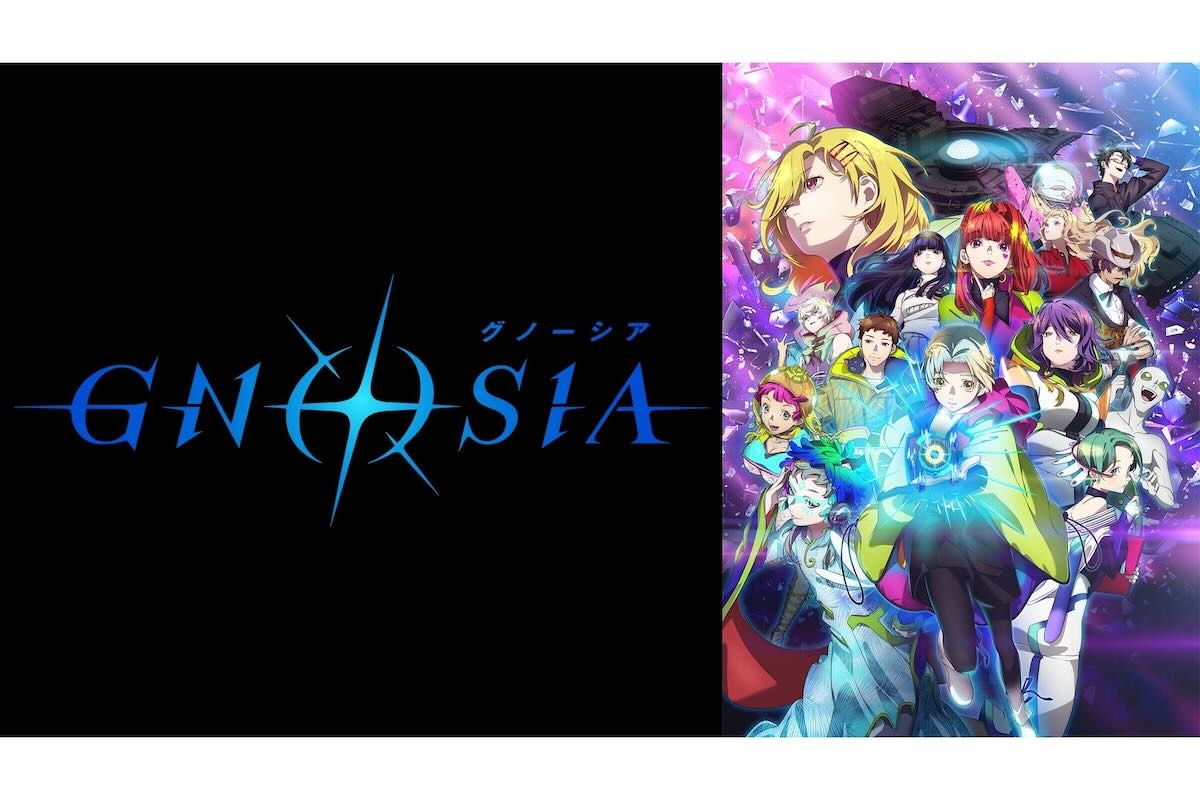
アニメ化への不安を払拭した『グノーシア』
TVアニメ『グノーシア』が各所で大きな話題を呼んでいる。近年、原作がある作品のアニメ化となると、原作ファンからの厳しい目が向けられることも少なくない。しかし本作に対しては、原作ファンも初見の視聴者も高く評価する声がSNSで目立っている。
(※以下、作品のネタバレを含む記述があります)
特筆すべきは、原作ゲームが人狼ゲームをベースにした作品だということだ。ゲーム原作のアニメ化が難しいのは、プレイヤー自身の体験やエピソードの取捨選択が課題になるという点が大きいように思う。原作での体験を忠実に再現しようとして冗長になってしまったり、分岐要素のある印象的なエピソードを省いた結果、中途半端になってしまったりすることも珍しくない。
特に人狼ゲームは、参加者それぞれの推理と発言、そして選択によって成立するゲームである。プレイヤー自身が議論に参加し、誰を信じ、誰を疑うかを決断することこそが醍醐味だ。実況動画であれば配信者の視点を通じて「議論をする」という核心部分を追体験できるが、アニメという形式でその面白さを伝えるのは極めて困難であることは想像がつく。
『グノーシア』の場合、この困難さはさらに増す。本作は、時間が何度も繰り返される“ループもの”の要素を組み合わせた作品であり、プレイヤーごとに全く異なる体験が生まれる作りになっているからだ。データ上では約6万5000回ものループが可能だということを原作者が明かしており、エンドを迎えるまでに多くのプレイヤーが100ループ以上を経験することになるゲームでもある。
ループごとにイベントの出現パターンが異なったり、プレイヤーが選択する主人公の性別によって他のキャラクターの反応が変化したり。同じゲームをプレイしているはずなのに、実況動画を見ても同じ体験にはならない、極めて個人的な「自分だけのグノーシア体験」を提供する作品なのである。この「個別性」こそが原作の最大の魅力であり、同時にアニメ化における最大の障壁でもあったのではないか。
加えて、ゲームの大半は宇宙船という閉鎖空間を舞台にした会議シーンで構成されており、派手なアクションシーンがあるわけでもない。キャラクターたちが円卓を囲んで議論する、静的な画面で進行する心理戦を、どのようにして23分のアニメとして成立させるのか。「これは本当にアニメ化できるのだろうか」という不安を抱いていた原作ファンも多かったはずだ。
しかし蓋を開けてみれば、アニメ版はその高い壁をクリアする工夫が随所に見られた。最大の工夫は、記憶喪失のオリジナルキャラクター「ユーリ」の導入だろう。原作のことりが原案を担当しているだけあって、ユーリは原作のキャラクターたちの中に自然に馴染んでおり、全く違和感がない。
視聴者はユーリの目を通して、グノーシアとは何なのか、この宇宙船で何が起きているのか、各キャラクターはどんな人物なのかを少しずつ理解していく。ユーリが「何もわからない」状態から物語を始めることで、初見の視聴者と知識レベルを同期させているのだ。原作ファンには新鮮な再体験を、初見視聴者には自然な没入を提供する「案内役」の存在が、ゲームでは当たり前だった「プレイヤーの参加感」をアニメという形式で再現することにつながっている。
構成・脚本の手腕と豪華キャストもクオリティを支える
シリーズ構成・脚本を担当する花田十輝の手腕も見逃せない。『ガールズバンドクライ』『響け!ユーフォニアム』『メダリスト』とさまざまなジャンルの人気作を手がけてきた花田だが、本作ではループものという特殊な設定の活かし方が実に巧みだ。
第3話では人狼ゲームの占い師ポジションに相当する「エンジニア権限」が登場するほか、投票結果を活用して議論の勝ち筋が見えてくるなど、段階的にゲームシステムと設定を開示していく構成も、初見の視聴者に優しい作りになっている。各キャラクターの印象的な見せ場の配置も絶妙だ。ジナとの宇宙空間での“共同作業”の描写など、原作プレイヤーなら「あのシーンがこのタイミングで来るのか」と驚かされる構成が多い。
宇宙船内という限られた舞台でありながら視聴者を飽きさせないのは、原作では数十回、時には数百回と繰り返すループを、限られた話数の中で効果的に見せる工夫が随所にあるからだ。「次のループではどうなるのか」という期待感を維持しながら、同時に謎を少しずつ明かしていく。週に1話ずつ放送される連続アニメの特性をうまく活かした構成と言えるだろう。
宇宙船の船内が舞台であるがゆえに、どうしても静的になりがちな映像にも、アニメならではの演出が随所に加えられている。例えば第1話でSQがグノーシアとしてユーリを狩る回では、水槽の魚がキャラクターたちの状況を暗示する描写が印象的だった。
ゲーム原作のネタバレを避けるため多くは語れないが、おそらく水槽にいるSQのような魚がベタ(闘魚)をモチーフにしているのも示唆的である。色鮮やかなヒレを持ちながら、縄張り意識が極めて強く、同種の雄同士を同じ水槽に入れると激しく戦うこの魚がSQに重ねられていることそのものに意味を感じる。こうした細かな演出が、原作の世界観を尊重しながらも、すでにキャラの背景を知っている原作視聴者をも楽しませる表現としてアニメの世界を豊かにしていた。
そして本作のキャスティングの豪華さも見逃せない。ユーリ役の安済知佳を始めとする声優陣の顔ぶれは、公開前から大きな話題となっていた。怪しい者を炙り出すための会議シーンが多く、いわば会話劇が中心である本作では、ベテランキャストたちの掛け合いを心ゆくまで楽しむことができる。現段階ではまだ全キャラクターが登場していないが、これから新たなキャラクターたちがどんな声で、どんな演技で描かれるのか、その期待もまた大きな楽しみの一つである。
原作が持つ「自分だけのグノーシア体験」という魅力を、全員が同じ映像を見るアニメでどう表現するか。その挑戦はまだ始まったばかりだが、東京ゲームショウや学祭でのトークセッションを聴いていると、原作サイドとアニメ制作チームが密に連携しながら、互いの仕事にリスペクトを持って取り組んでいることが伝わってくる。好評の要因は多々あると思うが、大前提として原作サイドとの信頼関係が、作品のクオリティを支えていることは間違いない。
『グノーシア』のアニメ化は、原作の世界を尊重しながら新たな魅力を加え、ゲーム原作アニメの新たな可能性を示した成功例となるのではないか——そんな予感が、すでに漂い始めている。
 あなたの“気になる”を教えてください
あなたの“気になる”を教えてください
