
つかこうへいさんは「天才」 神尾佑が明かす素顔、台本なく「しゃべったセリフは全部覚えてる」
俳優・神尾佑が今年度をもって解散する劇団「★☆北区AKT STAGE」の解散公演第1弾『つか版・忠臣蔵』(7月10日初日、東京・北とぴあ つつじホール)で初めて演出を担当する。台本作りにも初めて挑んだ。1994年に結成された北区つかこうへい劇団の1期生として劇作家で演出家のつかこうへいさんの芝居を体感した神尾。公演前に取材に応じ、作品に込めた思いやつかさんの驚きの稽古など思い出も明かした。
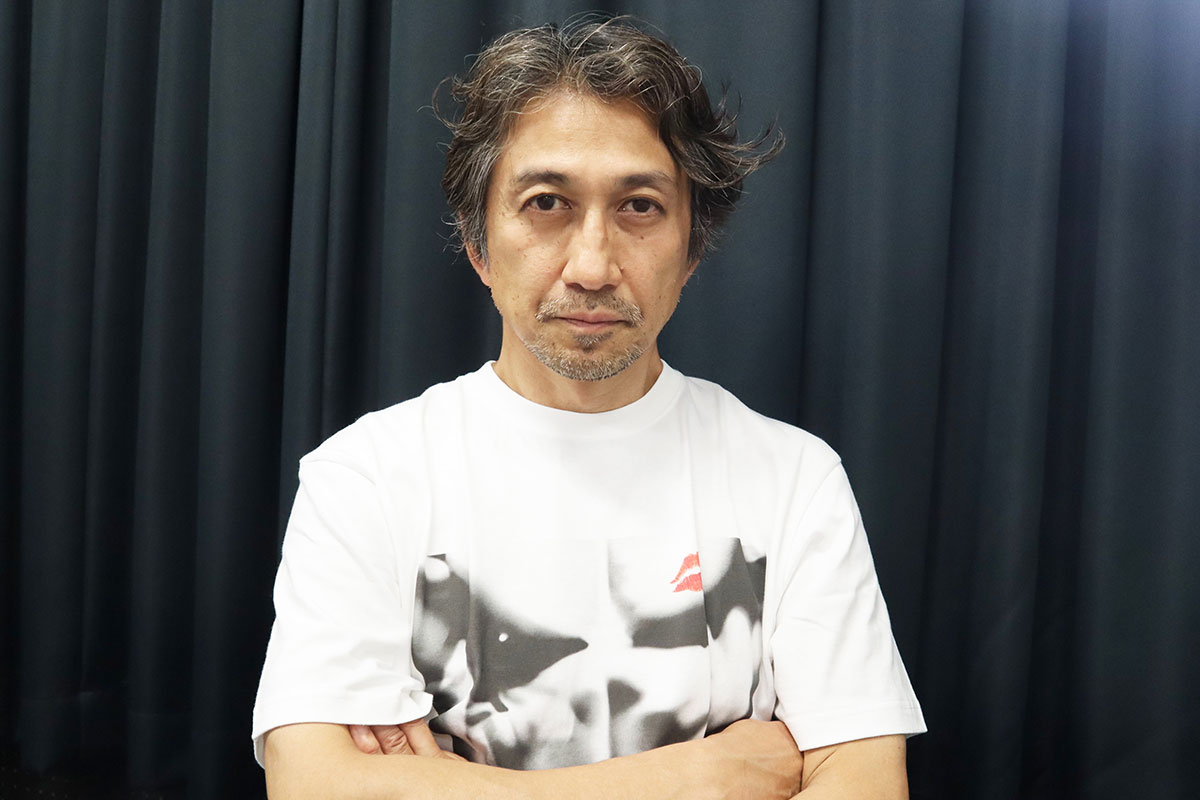
劇団「★☆北区AKT STAGE」の解散公演第1弾『つか版・忠臣蔵』7月10日初日
俳優・神尾佑が今年度をもって解散する劇団「★☆北区AKT STAGE」の解散公演第1弾『つか版・忠臣蔵』(7月10日初日、東京・北とぴあ つつじホール)で初めて演出を担当する。台本作りにも初めて挑んだ。1994年に結成された北区つかこうへい劇団の1期生として劇作家で演出家のつかこうへいさんの芝居を体感した神尾。公演前に取材に応じ、作品に込めた思いやつかさんの驚きの稽古など思い出も明かした。
まずは作品について尋ねた。
「1982年頃に書かれたつかさんの小説があり、テレビ東京でドラマ化されているのですが、実はきちんと戯曲化されていなかったです。この演目を決めた時にそれを知り、脚本を作ることから始めました。小説をベースにドラマの脚本も手に入れ、双方を照らし合わせながら脚本を作りました」
小説はつかさんらしさを感じる内容とされる。
「こんな発想を普通はしないだろうという切り口。すごいです。浅野内匠頭が“バカ殿”で家臣にも相手にされていない設定。だから家臣たちは殿のために討ち入りする気なんてさらさらないんです。そんな家臣が討ち入りする気になるか? という小説です。忠臣蔵は人情も詰まっていて日本人は好きですよね。そんな話をひっくり返す勇気とエネルギーは相当です。批判を恐れず、誰もが知っている話をひっくり返す着眼点はすごい」
台本は小説に忠実なのか。
「忠実にと思ったのですが、つかさんは芝居を作り上げていく過程で変化することを恐れなかった人。小説とドラマ版でロジックが逆転している部分もあるんです。どっちにすればという部分は自分なりにアレンジして僕が面白いと思うものを作ろうという気持ちで臨みました」
劇場にはつかさんを感じたくて足を運ぶ観客がいるかもしれない。公演への思いを聞いた。
「劇団の解散公演の第1弾で、解散という節目が自分の中では最も大きいこと。31年前に24歳で★☆北区つかこうへい劇団に入り、つかさんが亡くなって劇団名が変わってもずっとやってきましたから。つか作品を常にやり続ける劇団が消えるという節目、僕が育った場所が無くなる……だから今回の公演は僕の青春の総括、ノスタルジーなんです」
その思いは神尾個人の話ではない。
「20代の時の汗、稽古場のにおい、劇団みんなの熱量、つかさんが存在していた感じ……ここで過ごした劇団員の青春、思いが凝縮されれば劇団の解散の節目になるかと思います。そんな劇団員それぞれの思いを感じてほしいです。劇団を応援してくれた人たちと一緒に一区切りつけられたらと思います。つかさんの芝居は、その時、生で見たお客さん、演出を生で受けた人にしか分かりません。今回の作品が“つか芝居”と言われるかはお客さん次第。僕の中では今回の舞台はつかさんと過ごした僕ら劇団員の総括です」
そんな思いの中、つかさんを感じる部分はあるようだ。
「劇中で流れる曲、セリフ回しにはつかさんを感じる部分があると思います。特に楽曲は昭和の曲じゃないと合わないんです。僕が選曲したのはダウン・タウン・ブギウギ・バンドの『身も心も』。ドラマのエンディング曲でした。あの時代の哀愁、においを感じる曲。歌詞に人生が投影されています。そうでないとつかさんの芝居に合わないと思いました。つかさんの芝居で象徴的なのは人が生で1対1でぶつかり合うこと。似合うのは昭和の楽曲。その意味で懐かしいと思う人はいると思います」
つかさんの思い出も語ってもらった。すると驚きの稽古の実態が……。
「後から先にもつかさんのような人に出会ったことはありません。稽古の時は、ぼそぼそとつかさんが言うセリフを、言い方も含めてまるっきりマネするんです。つかさんの発するセリフを耳で聞いてマネして相手にぶつける。だから事前に台本をもらうことはありません。つかさんが『おい、おまえ、そこに立て。曲流せ』と言うと、キャストにその場でセリフを言い伝え、しゃべらせることを何往復もやります」
稽古の中の印象的な姿も紹介した。
「僕の横に来て、ぼそぼそとセリフをしゃべるのですが、つかさんの視線は相手の顔に向いています。そのセリフが相手に刺さっているか、演技ではない生の感情でどう反応するか顔を見て確認しているんです。そうやって琴線を探してセリフを作っていく。違うと思えばその場で別のセリフを考えます。だから事前に台本がないんです。その場でセリフを覚えないと『おまえ、いらん。代われ』と言われ、ほかの人間に役が振られてしまいます。だから稽古はすごい緊張感に包まれていました。僕はつかさんが来る3時間前には稽古場に行っていました。テクニックとかは一切教えてもらっていませんが、つかさんの生むセリフで汗をかき、涙を流し……面白かったんですね」
演出はつかさんを参考にしているのだろうか。
「できません。つかさんのように湯水のように言葉は出てきませんから。つかさんは天才。その場でどんどんセリフが出てきて、かつ我々に刺さる。そして、しゃべったセリフは全部覚えているんです。公演中でもよくセリフを変えていて、劇場に着いたら稽古をしていることもありました。いつ何時、何が起こるか分からない。恐怖です。だから自分からつかさんに話しかける人はほぼいなかったです(笑)。居酒屋でも誰もしゃべらず、つかさんだけしゃべっていました」
最後に意気込みと今後の目標を聞いた。
「つかさんが作品に込めた思いは分かりませんので僕なりの解釈で作るしかないと思って臨みました。脚本がないので、つか作品の焼き直しもできませんでした。つかさんのふんどしをお借りして新たな相撲を取ります。今後の目標は……演出はやってみたいです。向いていると思ったんです(笑)。俳優を軸に、今まで自分が培ってきたことをベースにできる限りのことをやってみたいです」
 あなたの“気になる”を教えてください
あなたの“気になる”を教えてください
