
過激化する格闘技に「気味が悪い」 医師がビンタ大会に明かす胸の内「心から治療したいとは思えない」
エキサイティングな格闘技への人気が高まるなか、素手でボクシングを行うベアナックル・ボクシングや、ノーガードでビンタを順番に打ち合うパワースラップが日本に上陸した。総合格闘技大会にリングドクターとして従事した経験を持つ、医療法人あんず会杏クリニック院長の鬼澤信之氏は「競技として認めたくない」と語る。その理由とは。

スコットランドでは初のパワースラップ大会が中止に
エキサイティングな格闘技への人気が高まるなか、素手でボクシングを行うベアナックル・ボクシングや、ノーガードでビンタを順番に打ち合うパワースラップが日本に上陸した。総合格闘技大会にリングドクターとして従事した経験を持つ、医療法人あんず会杏クリニック院長の鬼澤信之氏は「競技として認めたくない」と語る。その理由とは。(取材・文=島田将斗)
パワースラップは米国で人気の平手打ち対決イベント。参加選手は体重別に分けられ、先攻・後攻を決めて交互にビンタを打ち合う。その際、受ける側は一切ガードが許されない。相手をパワーで倒すか、打撃に耐え抜くか──脳を揺らされながらの我慢比べとなる。勝敗はKO、TKO、判定で決まる。
米国では『パワースラップ』としてテレビ放送・配信され、日本では格闘家の朝倉未来氏が社長を務める格闘技エンタメイベント「BreakingDown」で、今年1月に初実施された。
一方、今年2月にスコットランドで開催予定だった初のパワースラップ大会は、健康上の懸念から中止となったと、英国の公共放送BBCが報じている。
まさに議論を呼ぶ「ビンタ大会」について、鬼澤氏は「認めたくない」と強い口調で断じる。医師としての立場から、その存在自体に疑問を呈した。
「パワースラップは、医師の視点から見ると競技として納得も理解もできない。ベアナックル・ボクシングは『過激な競技』として成立しているが、パワースラップは“必ずダメージを受ける”ことが前提になっている。程度の差はあれ、そうした外傷を負って病人として治療を受けてよいのかという疑問がある。また、表面には分からないダメージが蓄積していく点も気味が悪い。現時点で大丈夫でも、将来的にどうなるか分からない人に対して、医療者がどこまで健康への責任を取れるのか、という問題です」
鬼澤氏はさらに声を強める。「僕としては、競技として認めたくない」と言い切った。
「なぜなら、あれは自分からダメージを負いにいっている行為だからです。わざわざケガをしに行っている人を、医療者は心から治療したいとは思えない。自傷行為に近いものを感じます。当然、税金を使った保険医療を提供することはできないと思います。他の格闘技では、技術の応酬の中でケガを負う。そこには“避ける”という選択肢もある。でもパワースラップは、ケガを避けることが前提にない。だから自傷行為と本質的に変わらないのではと感じます」
他の格闘技にも失神や重傷を伴うシーンはあるが、それは技術を尽くした末に結果的に負ったものだ。そもそも選手たちは、傷を避けつつ勝つことを目指している。
「これまで、競技中にケガを負った選手を治療する際に、リストカットのような自傷行為で負った傷を縫うときのような気持ちになったことは一度もない。選手の“名誉の損傷”には敬意がある。挑戦の代償としての傷に、医師として誇りを持って対応できた。だから真剣勝負の場には感動がある。一方、自傷行為の患者さんには、やるせない気持ちになりますよ」
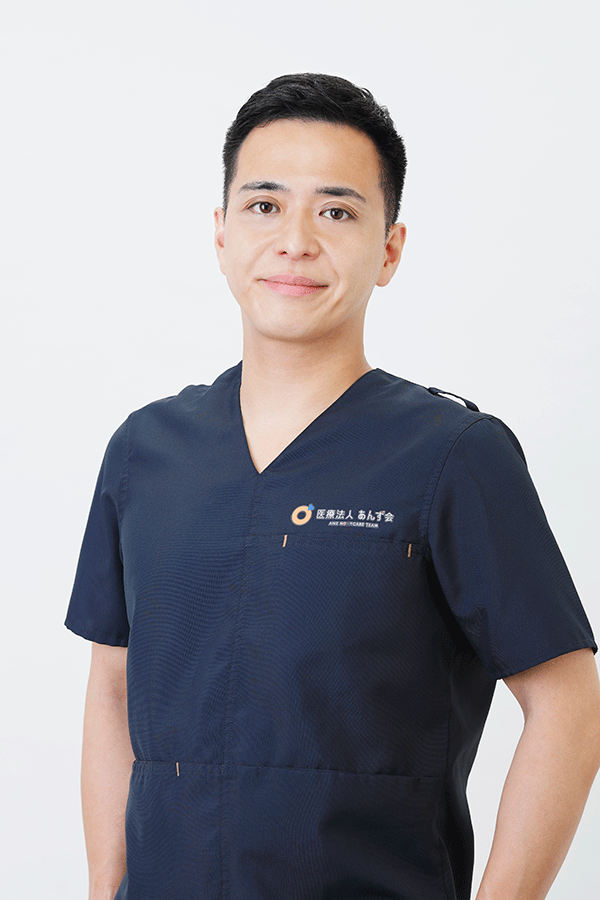
日本が公的医療保険制度であるがゆえの議論も
もっとも、パワースラップを「見て楽しむ」視聴者がいるのも事実。分かりやすい競技性が、ジャンルのすそ野を広げている側面もある。
「選手もドクターも、やりたくなければやらなければいい。ただ、過激化が進むことは人間の本能かもしれないが、医療者としては『ケガのリスクは確実に高まる』という点を強調しなければいけない。ベアナックルが安全という人もいますが、それは違うと思う。医療者は、誰かにケガをしてほしいとは思っていません。すべての人の健康を願うのが医師です。だから、健康と報酬を引き換えにするような過激化は避けてほしい」
特に日本では、保険診療制度がある。つまり、税金によって誰もが医療を受けられる仕組みだ。
「絶対にケガを負う前提の競技に参加して、そのまま保険証で治療を受けていいのか──。そういった議論が出てくるのは当然です。もし本当に必要な病気の人が救急車を使えなかったとしたら? という問題もあります」
安全確保には医療体制の整備だけでなく、制度的な議論も必要だ。米国には公的医療保険制度がないが、日本は違う。
「だからこそ、パワースラップのような競技は“どういう契約で行うのか”を明確にすべきです。ケガの医療費は誰が払うのか。障害が残ったときの責任は誰にあるのか。なにか起きてから医療者の責任にされても困ってしまいます。ルールを曖昧にしたまま、若者の好奇心や過激性への誘惑に任せてはいけない。選手も『ケガをすれば自分で責任を取らないといけないかもしれない』というくらいの覚悟は必要だと思います」
「BreakingDown」の台頭や、フィットネスを通じた格闘技人気の高まりによって、格闘技はかつてよりも“身近”になっている。それ自体は良い傾向だが、安全とリスクの議論は置き去りにされている。
数字のためではなく、文化として格闘技を未来へ残していくために──。鬼澤氏の真摯(しんし)な問題提起は、医療者としての立場だけでなく、格闘技を愛する一人としての願いでもある。
 あなたの“気になる”を教えてください
あなたの“気になる”を教えてください
